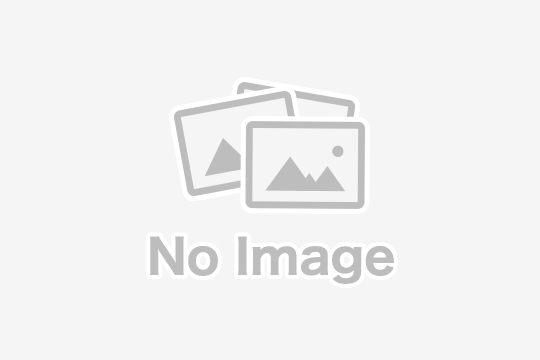子どもが学校に行きたくない、休みたいと聞くと親は苦しくなるものです。何かきっかけがあったにせよ、学校に行くエネルギーがなくなるのは、長期的なエネルギーの消耗で起きています。
学校で嫌なことがあっても、乗り越えるエネルギーがあれば学校に行くことはできます。学校や家で傷ついて、無理に無理を重ねて学校に行けなくなった状況がいわゆる不登校です。
今まで傷ついてエネルギーが回復していない状況を、学校に行かないという行動に表すことができたことは、親からすると苦しい状況ですが、子どもたちにとっては回復の第一歩だと見ることができます。
回復の第一歩を踏み出したときに、してはいけない対応は無理やり学校に行かせたり、学校に行かないことを責めたりすることです。
まずは、今までしんどかった状況をくみ取り、家で安心して過ごすことのできる環境にすることが必要となります。ゲームばかりしてしまう、昼夜逆転する、保護者からすると焦ってしまう状況ですが、エネルギーななくなっているからこその行動であることを理解しておく必要があります。勉強はかなりのエネルギーがたまったときにできることなので、本人が必要とし自主的にやらない限り、強制しないようにしましょう。今は学び直しも含めて多様な学びが用意されつつあります。
学校を休んでいる間に必要となることは、親子間の穏やかな会話となります。学校を休んでいることを受けとめ、何が苦しかったのか、今は少しずつ元気になっているか、今困っていることは何かなど、子どもが言葉にできる機会を焦らず、ゆっくりとつくりましょう。保護者の関わりでしんどい状況が生まれていたとわかったら、素直に謝る必要もあると思います。
保護者の元気と学校に行っていない子どもの元気は連動しています。子どもが学校に行っていないと、保護者の元気はなくなりがちです。例えば、子どもが学校に行っていないことを周りから責められたお母さんは、ますます元気がなくなり、学校に行けない状況はより悪化することになります。
学校に行っていない子どもを元気にするために、保護者が少しでも元気になることが求められています。そのために、いろいろな人に相談にのってもらい、苦しさや辛さを保護者が抱え込まないようにする必要があります。
保護者が元気になって、親子で何かを一緒にできる機会もつくることが可能なら、回復を早めるかもしれません。ただ、親子関係がかげを落としている場合は、少しずつ親子関係を修復する必要があるので、子どものペースに合わせて回復していくことが求められます。
何かやりたいこと(絵を描く、運動する、楽器を始める、人と交流する)が出てきたら回復が進んでいる証拠です。ゲームに依存することもありますが、自分の居場所として機能していることもあるので、無理に取り上げても回復にはつながりません。ゲームで活躍している場面があれば、一緒にやったり、褒めたりすることで、エネルギーが回復することもあります。
子どもたちのSOSを責めずに、寄り添い一緒に考え、子どもの声をきく姿勢が、不登校や問題行動の唯一の解決策です。