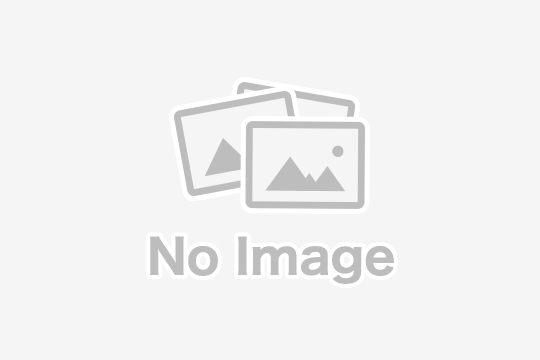不登校者数の増加が報道で大きく取り上げられています。まず不登校という言葉をやめませんか。
登校、下校、学校は高い位置にあるのでしょうか。登城、下城、いつの時代でしょうか。明治時代に決めた学校の制度がそのまま残っているところが、学校にはまだたくさんあります。子どもたちが時代に合わない学校の状況に悲鳴をあげているのだと思います。
学校の先生への成り手が減っているという報道もたくさんあります。今の学校の在り方に苦しんでいる子どもたちが増えているのに、受け入れる側の大人が集まらない状況です。既に教職についている先生たちも疲弊している状況があります。
学校に行きにくい子どもたちを責めるのをやめましょう。学校に行けないことで、責められている子どもたちをたくさん見てきましたが、責められることで改善した子どもは一人もいません。むしろ悪化するか、大人になってからより大きな問題に発展することになります。
子育ての根はいつも子どもの思いにまず耳を傾けることです。もしかしたら、言葉にできないかもしれません。学校に行けない、問題行動を起こす、すべて子どものSOSです。言葉にできないなら、まずは苦しい状況にあることをわかってあげてください。その状況を責めたら、子どもたちはますます苦しい状況に追い込まれます。
子どもたちが立ち直るときはエネルギーがたまっていくときです。苦しい状況の受容が立ち直りの第一歩です。
学校に行かせたい、問題行動をなくしたい、気持ちはよくわかります。ただ、苦しさの積み重ねでのSOSです。解決には待つ姿勢と時間が必要です。